19. アメリカの鯨捕り、ジョン・マン by 櫻井敬人
(草の根通信82号、2015年2月掲載)
櫻井敬人: ニューベッドフォード捕鯨博物館顧問学芸員、太地町歴史資料室学芸員
2 0 1 4 年 秋、米 国 のエリック・ジェイ・ドリンが 著したアメリカ捕 鯨 全 史「Leviathan: the History of Whaling in America」の日本語訳「クジラとアメリカ:アメリカ捕鯨全史」が原書房から出版されました。その翻訳者の一人で、太地町歴史資料室学芸員およびニューベッドフォード捕鯨博物館顧問学芸員を務める櫻井敬人さんにご寄稿いただきました。
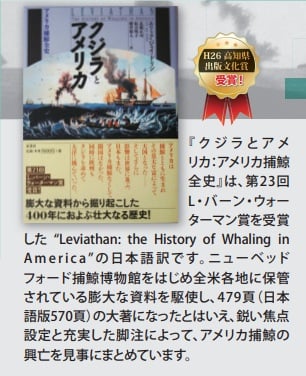
ジョン・マンこと中濱万次郎は、日本を離れていたおよそ10年間のうち、アメリカの2隻の捕鯨船上で約5年間を、そして捕鯨産業の中心地であったマサチューセッツ州ニューベッドフォード周辺で約3年間を過ごしました。つまり日本を離れていた時間のほとんどをアメリカ捕鯨産業の中に身を置いていたのです。日本を離れていた間の経験が万次郎の人間形成に大きな影響を与えたというのであれば、彼をより良く知るためには、当時のアメリカ捕鯨産業を知ることが肝心であるといえるでしょう。
ジョン・マンがニューベッドフォード対岸の町フェアヘイブンで暮らしていた頃、世界中の捕鯨船およそ9 0 0隻のうち、700隻超が米国東海岸から出港していました。なかでもニューベッドフォードからの船がおよそ300隻で群を抜いていました。ペリー提督が浦賀へやって来た1853年、アメリカの捕鯨船は世界中の海で8,000頭以上のクジラを捕え、5,700万リットルを上回る鯨油と大量の鯨髭製品を生産して、1,100万ドルもの売上を記録しています。綿織物産業などと並んでアメリカで最も重要な産業のひとつであった捕鯨は最盛期を迎え、莫大な富をもたらしていたのです。
豊かな捕鯨漁場を求めて、アメリカの捕鯨船はホーン岬を越えて太平洋に進出し、1819年にハワイに到達して、さらに西進していきました。そこで豊かなマッコウクジラ資源を発見すると、ハワイから日本沿岸に至るまでの広大な海域は「ジャパン・グランド」呼ばれるようになりました。この捕鯨漁場を目指して日本沿岸にまでやってきた船のなかにジョン・ハウランド号があったのです。足摺岬沖から漂流し、鳥島に流れ着いた万次郎と他の4名は、ウミガメの卵を採取するために鳥島に近づいた同船によって救出されました。

絶頂期にあったアメリカの捕鯨船は常に人手が不足しており、グリーン・ハンド、つまり海での経験に乏しい青二才がたいてい数名乗船していました。病気や怪我による下船だけでなく、厳しい仕事を嫌って帰港地で逃亡するものが後を絶たず、船は寄港す先先々で船員を雇い入れるので、船内の男たちの顔ぶれは多彩でした。ジョン・マンは決して珍客ではなかったのです。もちろん船長や航海士は白人が多く、非白人と同等に扱われた彼らが文句を言わなかったわけではありません。しかし当時、アメリカではまだ奴隷制度が合法であったことを考えれば、出自に関わらず、働きに応じて報酬が支払われたアメリカ捕鯨の世界は、ジョン・マンの目には公正な社会として映ったことでしょう。
ジョン・ハウランド号を降りて、船長の庇護のもとにフェアヘイブンで暮らす間も、ジョン・マンは優れた鯨捕りになるために努力を続けました。まずルイス・バートレットが 経営する学校で航海術を学んだといわれています。また鯨油樽を作る技術を身につけています。樽職人の報酬は3等航海士のそれと並ぶほどでした。1846年5月、フランクリン号で2度目の捕鯨航海に出港したとき、ジョン・マンは3等航海士に次ぐスチュアードという身分を与えられています。グリーン・ハンドの上の平船員の、もうひとつ上の格です。船長の身近に控えて世話をすることに加えて、船内の食糧管理が主な仕事でした。フランクリン号は東進してアフリカ西岸を南下し、喜望峰、インド洋を越えて日本沿岸に至っています。

なお万次郎の長男、中濱東一郎が昭和11年(1936)に出版した『中濱萬次郎傳』には、フランクリン号の船長が発病してマニラで下船した後、船員同士で投票した結果、ジョン・マンが「副船長」に選ばれたという話が出てきます。しかしそれを裏付ける資料は発見されていませんし、そもそも副船長という役職はアメリカの捕鯨船には存在しません。ただし捕鯨船に搭載されていた捕鯨ボート内で第2番目の地位にジョン・マンが押し上げられたとする解釈があります。捕鯨船には3艘から6艘の、6人乗りの捕鯨ボートが載っています。クジラを追うために海面にボートを降ろした後、船尾で舵を取り、指揮するのは航海士の役目です。それに次ぐ役職が船首に立つ銛打ちで、さらにオールを漕ぐ4名の水夫が加わります。船長がマニラで下船した後、1等航海士が船長になり、以下順繰りに昇格して、ある1艘のボートのなかでジョン・マンが水夫から銛打ちに取り立てられたと考えることに無理はありません。
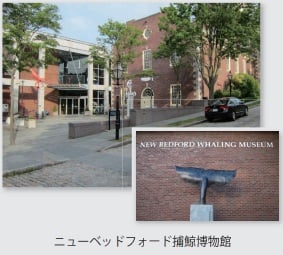
アメリカ捕鯨では、不漁のまま帰港すれば船長は欠損の責めを負わされるばかりか、不運もしくは無能の船長として疎んじられました。したがって満船になるまで航海は続けられ、通常3年間を超えるようになっていました。捕鯨船の暮らしに倦んだ男たちがいつも考えていたのは、クジラを獲りまくって一日も早く母港へ帰ることでした。言うまでもなく捕鯨の成否は銛打ちの双肩にかかっています。アメリカの捕鯨船上では、出自はともかく、鯨捕りとしての責任を良く果たすかどうかが重要でしたから、優れた銛打ちの技術を持ち、仲間が信頼する男でなかったとすれば、ジョン・マンがその重職に就くことはなかったでしょう。

アメリカの捕鯨帆船で唯一現存するのは、1841年にニューベッドフォードで建造されたチャールズ・W・モーガン号です。2014年夏、大掛かりな修復を終えました。所蔵るミスティック・シーポートのビートー理事長が、進水式で興味深い指摘をなさいました。モーガン号は、「自由(freedom)」、「自立(self-reliance)」、「勇気(courage)」、そして「個人の責任(personal responsibility)」という、アメリカ人が最も重視する価値観を体現しているというのです。つまり世界中からやってきた人々が乗り組んでいたアメリカの捕鯨船は、異なる生い立ちを持つ移民たちによって形作られたアメリカという国を象徴しているということでしょう。我々が中濱万次郎に惹かれるのは、漂流と無人島を経たアメリカ捕鯨の生活のなかで、自らを頼りにして活路を開いていったジョン・マンの生き様が、多様な価値観の渦の中で右往左往する現代人を勇気付けるからではないでしょうか。
