14. ジョン・ハウランド号の『航海日誌』世に出る [前編] by 川澄哲夫
(草の根通信73号、2013年2月掲載)
川澄哲夫:CIE評議員、文学博士・元慶応義塾大学教授、ニューベッドフォード捕鯨博物館・学術顧問
『ライマン・ホームズの航海日誌』は、2001(平成13)年2月、神田の古書展(小川図書出品)で小沢一郎氏が入手し、永く刊行が待たれていた書である。原典は現在、財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センターが管理している。
この航海日誌は、ライマン・ホームズというgreen hand(新参水夫)が、3年6ケ月と7日にわたって克明に記した記録である。彼の英語は正確そのもの。雨にも負けず風にも負けず、鯨を追いかけた日も、解体作業に疲れ果てた夜も、日記を書き続けている。鯨に頭突きをくわされ、ボートを木っ端微塵に打ちくだかれ、海に放り出されたことまで日記に書き留めている。ホームズが乗り組んだのは18才。ほぼ大学4年間を捕鯨船上で過ごしたことになる。
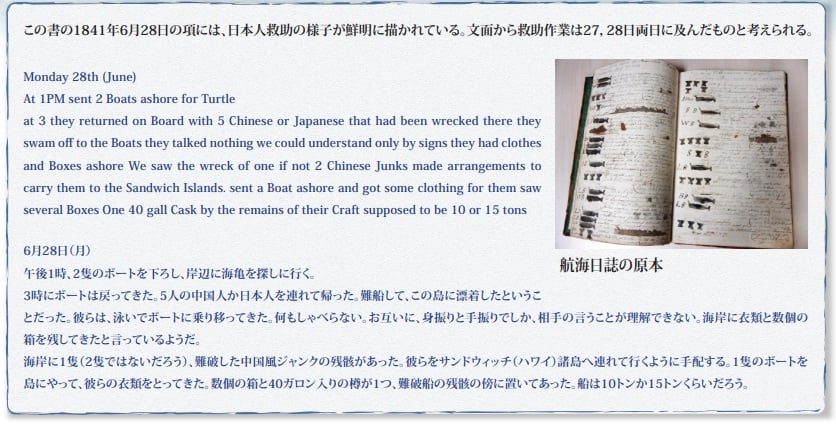
ジョン・ハウランド号は、1839年10月31日、ニューベッドフォードを出帆して、太平洋・日本漁場へ向かった。乗組員は船長ホイットフィールド以下28名、ライマン・ホームズ(Lyman Holmes)はgreen handの一人としてこの航海に加わっていた。ライマン・ホームズの航海日誌は、11月26日ベルデ岬諸島が見えるところから始まる。おそらくホームズは、鯨捕りとしての最初の航海なので、船酔いを克服したり、無数にある捕鯨船上の仕事に馴れないため、日誌をつける余裕がなかったのであろう。このあと、ジョン・ハウランド号は、南西に進路をとり、ブラジル沖、フォークランド諸島の沖合を過ぎ、やがてホーン岬を周って太平洋に出た。ホーン岬は、南米を迂回して太平洋に抜ける航路中最大の難所である。
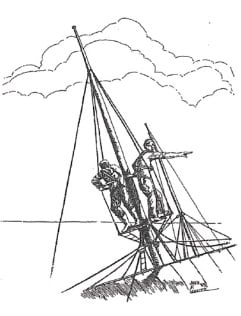
太平洋に入ったジョン・ハウランド号は、南米の西海岸に沿って、マッコウクジラを追いかけながら北上する。4 月 24 日、ペルーのカヤオ港に錨を下ろした。そこから西北に進路をとり、遠海漁場(Off-shore Grounds)へ向かった。そうしてマーケサス諸島、ソシエテ諸島近海、さらにニュージーランド沖まで南下してマッコウクジラを追いかけた。
そのあと太平洋の中心に出てナビゲーター(サモア)諸島、キングズミル(ギルバート)諸島沖で、それぞれの季節に合わせてマッコウクジラを追いかけた。それからカロリン群島中のアセンション(ポナペ)島に立ち寄り、薪水・食料を補給した。そのあと、ジョン・ハウランド号は、ラドローン(マリアナ)諸島の最先端にあるウラッカス島に向け進路をとり、1841年5月6日にボニンズ(小笠原群島)を望見できる位置に達した。アメリカの捕鯨船は、グアム島に20日ほど滞在して、ゆっくりと薪水食料を補給し、日本漁場でのマッコウクジラシーズンに備えるのが普通である。ところが、ジョン・ハウランド号は、グアム島に立ち寄らないで日本漁場へ直行したのである。そうして6月27日、Deniso(筆之丞)、Mongo(万次郎)、Jusica(重助)、Trimo(寅右衛門)、Guimo(五右衛門)の救助となった。

ジョン・ハウランド号は、漂流民を乗せたまま、孀婦岩と鳥島を中心にマッコウクジラを追い続ける。日本漁場での捕鯨シーズンは5月から9月末まで、まだ始まったばかりである。1841年7月7日、無人島を離れて10日目に、ジョン・ハウランド号は、2頭のマッコウクジラを仕留めた。
9月10日になって、ジョン・ハウランド号は、進路を東南にとった。10月11日、北緯30度、東経169度の地点で、雄のマッコウクジラ2頭を捕った。今シーズンの日本漁場での収穫は全部で28頭、1千バレルのマッコウ油がとれた。

1841年11月22日、ジョン・ハウランド号は、ウワホー(Oahu)と申す島のハロナロ(Honolulu)へ入港した。日本ではその前日の11月23日(天保12年10月11日)、渡辺崋山が自刃して果てた(時差を考えれば同じ日)。モリソン号事件の余波である。「ハロナロ」湾には、チャールズ・ウィルクス大尉率いる太平洋探検隊の4隻の軍艦が目を惹いた。この艦隊は3日前の17日に入港していた。彼らの目的のひとつは、太平洋海域の風、潮流、各地の風習などを調査して、アメリカの鯨捕りたちが安全に操業できるように協力することであった。
11月26日、ウィルクス大尉らは土佐の漂流民と出会う。「日本人は背が低く、知性に欠けている。彼らは多分下層階級の漁師であろう」という印象を受けた。画家アガテは日本人の一人をデッサンした。絵の主は万次郎か。

