11. 『ハート・オブ・ア・サムライ」の執筆にあたって』 by マーギー・プロイス
(草の根通信70号、2012年3月掲載)
マーギー・プロイス:米国の児童文学作家
翻訳:下村淳子
2010年にアメリカで児童文学賞を受賞した万次郞の小説『ハート・オブ・ア・サムライ』の著者マーギー・プロイスさんが、去る1月22日にダラスにて講演を行いました。そのお話の内容を要約してご寄稿いただきました。

数年前、ローダ・ブルームバーグさんが書いた絵本『Shipwrecked (難破)』の中で私は初めてジョン万次郞と出会いました。その時は予想もしていませんでしたが、この出会いがきっかけで私はたくさんの心ときめく経験をすることができました。日本をはじめアメリカ全土を渡り歩き、多くの人々と出会い、たくさんの友人をつくることができました。そして、私自身が書いた児童小説『ハート・オブ・ア・サムライ』を通してアメリカの子ども達にも万次郞について伝えることができたことに感謝しています。(日本でも集英社から『ジョン万 海を渡ったサムライ魂』(仮題)として6月末に発行予定です)
学校の子どもたちに話をする際に私はいつもこう言います。「皆さんに会いに来たのは、170年前に生まれた友情のお話をするためです。その絆があまりにも強かったためいまだにその友情は続いています」。
それから万次郞について話をします。1841年に鳥島で、彼とそして4人の漁師仲間を救った捕鯨船のホイットフィールド船長との出会いと、その後に育まれた友情について語ります。
たくさんの帆を掲げ、その縄梯子を昇り降りする大勢の水夫達を乗せたジョン・ハウランド号の様子は、万次郞にとっては驚くべき光景だったことでしょう。万次郞と4人の仲間はいまだかつてこのような船を見たことがなかったのではないかと思います。そしてこれはその後続く様々な驚くべき出来事の始まりでした。捕鯨船に乗った彼らを待ち受けていたのは数々の初めての経験でした。ナイフとフォークを使った食事、初めてのパンの味、ポケットやボタンのついた洋服、革のベルトや革靴、そして英語での会話(船上の人々が話していたであろうその他の全ての言葉もしか)。椅子に座ることでさえ彼らにとっては初めての経験だったかもしれません。そして、背の高い、ひげの生えた、鼻の大きい目の青い人々。それまで「野蛮人」と言われている人達について聞いたことはあったとしても、実際に出会ったのは初めてだったことでしょう。確かに西洋人は色々な意味でその「野蛮人」に当てはまる一面を持っていたかもしれません。大きくて、毛深く、礼儀知らずで、手で物を食べ、荒々しい捕鯨に携わっていた。そしてクジラを捕っていた故に本当に臭かったと思います。
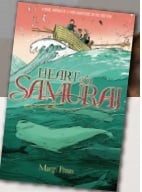
それにもかかわらず、万次郞は思いもよらない行動をとりました。彼はこの人々と友達になったのです。万次郞は彼らの言葉を学び、船上で彼らの手助けをし、わからないことは聞きました。彼は広い心を持ち続けました。生徒達に私が言っているのは、この友情の絆はとても強く(普通ではありえない友情だったからこそかもしれません)、今でも続いているということです。両家が今でも友情で結ばれているだけではなく、その絆は「日米草の根交流サミット」という形で続いています。両家の間に続いている長い友情の絆が、多くの人々を結びつけ、彼らの間にも友情が芽生えていることを私は大変嬉しく思います。

私が話をした生徒達は両家の長く強い友情を知って驚き興奮しています。そして、万次郞の冒険に魅了されています。特に真実が作り話より信じがたいこともあるのです!
私のジョン万次郞との出会いのきっかけは、『The Peace Bell(平和の鐘)』という本と書く為に調べ物をしていた時でした。この本は、私の故郷ミネソタ州ダルースが千葉県大原(現いすみ市)と姉妹関係を結んだ実話に基づいた絵本です。両市の友情の架け橋となったのは昔からあった美しいお寺の釣鐘でした。この鐘も第二次世界大戦中には金属であるとして供出されましたが、なぜか溶解をまぬがれました。戦後日本に駐留していた米国戦艦ダルースの乗組員が横浜の造船所でこの鐘を発見し、戦利品として米国へ持ち帰ることにしました。そして、艦隊の名の由来となったミネソタ州ダルース市にその鐘を寄贈しました。その9年後、釣鐘が大原のお寺のものだったと知ったダルース市長は故郷の大原にお返しし、その鐘は日米友好平和の鐘と呼ばれるようになりました。その後何年もたってから両市は姉妹都市となり、その際にダルース市にも鐘が送られました。大原町は現在いすみ市に代わりましたが、今でも大変暖かい友情が育まれています。二つの鐘は毎年9月11日に同時に鳴らされますが、その音が海を越えて平和のメッセージを共鳴させられるよう、それにふさわしい場所に吊されています。

「The Peace Bell(平和の鐘)」の友情が、もう一つの友情である万次郞の話へとつなげてくれたのです。その後、『ジョン万物語』(文:田中裕美とウェルカム・ジョン万の会、絵:アーサー・モニーズ)という素晴らしい絵本や中濱京さんの『ジョン万次郞』という大変魅力的な本とも出会いました。
執筆には3年もかかってしまいましたが、個人的にはいいタイミングだったと思います。丁度この本に取りかかっていた時、アメリカはイラク戦争の真最中で、アメリカ人の多くがイスラム教徒に対して深い怖れを感じていました(今でもそれは続いています)。彼らのほとんどは平和を愛する人々であるのに、彼らに恐れと怒りが剥けられていることを私は悲しく思っていました。でも、万次郞について、そして彼をめぐる異文化間における相互理解と人と人、国と国との間の平和な絆について書くことで私の心は癒やされました。私が知る限り、このような話はそんなに多くありません。人は違うところよりも似ているところの方が多いということ、たとえ違いがあったとしても友情の妨げにはならないということを私達は常に自分に言い聞かせなければいけないと思います。
最後に子ども達への話を締めくくる時に私はいつもこのように言います。「万次郞は自分が世の中の動きに一役買うことになろうとは思ってもいませんでしたが、実際は大きな役割を果たしました。その全ては、彼が自分とは異なる人間と友情を結ぼうとしたことから始まったのです。これは私達みんなもできることです。ひょっとしたら私達もまた世界を変えていくことができるかもしれません」。
