1.万次郞夜話第1回 万次郞の救出 by 川澄哲夫
(草の根通信58号、2008年7月掲載)
川澄哲夫:慶応義塾大学名誉教授、ニューベッドフォード捕鯨博物館 学術顧問、CIE評議員
1841年6月28日、一隻の異国の捕鯨船が鳥島の沖合に錨を降ろした。ジョン・ハヲラン号である。当時、鳥島は、メリケンの鯨捕り仲間では、聖ペテロ島と呼ばれていた。奇しくも、聖ペテロ祭の前日である。
やがて、二隻のボートが降ろされ、この無人島に漕ぎ寄せて行った。海亀を捕えて、船上での食生活を潤そうと考えたのである。ところが、彼らは海亀の代わりに五人の人間を発見したのである。その様子をライマン・ホームズの「航海日誌」は、次のように語っている。彼は平水夫(green hand)で、世界漫遊旅行としゃれこんで、ジョン・ハヲラン号に乗り組んでいたにちがいない。
午後一時、二隻のボートを降ろし、島に海亀を探しに行く。三時、ボートは戻ってきた。五人の中国人か日本人を連れ帰った。難船して、この島に漂着したということだ。泳いでボートに乗り移ってきた。お互いに、身振り手振りでしか、相手の言うことが理解できない。島に衣類と数個の箱を残してきたと言っているようだ。海岸には、一隻(二隻であろうか)の中国風帆船の残骸があった。
一隻のボートを島にやって、彼らの衣類をとってきた。40ガロン入りの樽が一つ、難破船の残骸の傍に置いてあった。船は10-15トン位だろう。彼らをサンドウイッチ諸島(ハワイ)へ連れて行く手配をした。
万次郞夜話第2回 万次郞たちは船中のどこにいたか by 川澄哲夫
(草の根通信59号、2008年12月掲載)
川澄哲夫:慶応義塾大学名誉教授、ニューベッドフォード捕鯨博物館 学術顧問、CIE評議員
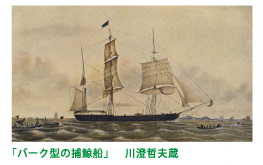
土佐の5人の漂流民は本船に移った。143日暮らした鳥島とも雨露を凌いだ洞窟ともお別れである。
翌朝、ジョン・ハヲラン号は「檣(ほばしら)ヲ建タル如き岩(孀婦岩(そうふがん))」の辺りを乗り抜け、抹香鯨を追いかけていった。
日本漁場での抹香鯨漁は始まったばかりである。万次郎たちが救助されて10日目には、抹香鯨2頭を仕留めた。その後もジョン・ハヲラン号は、孀婦岩(そうふがん)と鳥島を中心に、抹香鯨を追い続ける。やがて長かった日本漁場での捕鯨シーズンも終わりに近づいてきた。1842年9月10日、ジョン・ハヲラン号は、進路を東南にとり、日本沖を離れた。今シーズンの日本漁場で仕留めた抹香鯨は28頭、1000バレルの抹香油の収穫であった。
11月22日、ジョン・ハヲラン号は、オアフ島のホノルルへ入港した。万次郎たちは148日間、アメリカの捕鯨船で生活したことになる。
ところで、彼らは捕鯨船内のどこに収容され、どのように暮らしていたのであろうか。「取調記録」にも「漂流記」類のどこにも記されていない。この興味深い生活の様子が。
ちなみに、捕鯨船内の鯨捕りたちの部屋は厳格に区分されている。船長と航海士たちにはキャビンが与えられ、そこは船の最後部にある。水夫たちは船首にあるフォークスル(forecastle)と呼ばれる部屋で雑居している。キャビンとフォークスルの間、どちらかといえば、船尾に近く、スティアレッジ(steerage)がある。そこは羽指(harpooner)、樽造り(cooper)、船長付給士(steward)などに割り当てられている。いわば職人部屋である。
『時規(とけい)物語』は、越中富山の長者丸の漂流の記録である。そこには、彼らがアメリカの捕鯨船に救助された直後の生活の様子が興味深く語られている。
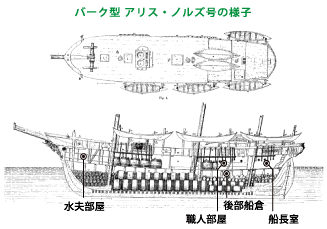
長者丸は、仙台唐丹(とうに)の港を江戸へ向かって出帆したところで、大西風に吹かれて、だんだんと沖へ流され、漂流を始める。船頭平四郎ほか、10人が乗り組んでいた。1839(天保9)年1月8日のことである。
長者丸は漂流しておよそ5ヶ月経った6月5日、生き残った7人が異国船に救助される。この船はナンタケ島(アメリカ捕鯨業の発祥の地)の捕鯨船「ゼンロッパ号」(James Loper)で、船長は「ケツカル」(Cathcart)といった。
ゼンロッパ号に移された長者丸の漂流民たちは、「ケツカル」の部屋へ案内される。そこで浅き茶碗のようなものに、米の粥(かゆ)を半合ばかり入れて、白砂糖をかけ、匕子(さじ)1本ずつ添えてだしてくれた。この同じ食物が昼から夕方にかけて、3度でた。これでみんな、「腰のぬけたるも直り」、元気になった。
夜になると、彼らは船の艫(とも)(船尾)に連れて行かれ、「人々集まりたる処に臥(ふせ)」った。ここには「日本船にて船の胴壁と申処に棚二段三段にしつらえてあり、それへ木綿のふとん、厚さ一尺余も有之をしき、からだの埋りたるようになり候上へ、赤或は白の氈(せん)を一枚覆ひ候て臥(ふせ)り申候」と描かれている。彼らはそこは「ケツカル」の部屋辺であったと語っているから、水夫部屋ではない。
また、メルヴィルの『白鯨』には怪しげな5人の水夫たちが乗っている。船長用のボートの乗組員である。彼らは他の鯨捕りとは離れて、船長室の真下にある後部船倉(after hold)にいた。万次郎たちもこの辺(あたり)で生活していたのではなかろうか。
